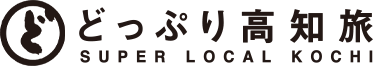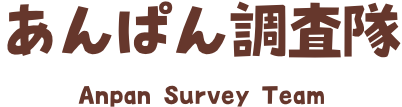あんぱん調査隊vol.8
高知の「酔い」魅力に迫る!
2025-06-20

★目次
1.「べく杯」と「おきゃく」文化
2. 人と人との絆を深める「返杯(へんぱい)・献杯(けんぱい)」の流儀!
3. 「はちきん」と「いごっそう」が育む酒豪県
4. まとめ:高知県独自の酒文化をぜひお楽しみください!
高知出身の漫画家・やなせたかしさんが主人公の夫のモデルとなる連続テレビ小説「あんぱん」。
第9週では、嵩の伯父・柳井寛が亡くなったときに、柳井家で、嵩の伯母・柳井千代子とのぶの母・羽多子が献杯するシーンがありましたね。
今回は、高知が誇る魅力の1つ「お酒」にスポットを当てたいと思います。

1. 「べく杯」と「おきゃく」文化
高知県の日本酒は、先日の全国新酒鑑評会で全国トップの入賞率となるほど評価が高く、県民は酒好きが多く、「酒国・土佐」と呼ばれる土地柄!そして、その日本酒を取り巻くユニークな「お酒文化」が根付いているんです。
高知の酒文化を語る上で欠かせないのが、「おきゃく」という文化です。これは、大人数が集まって酒を酌み交わす宴席のことで、結婚式や年季祝い、お花見の宴などで行われます。このおきゃくで使われるのが「べく杯(べくはい)」。底が尖っていたり穴が空いていたりして置くとこぼれてしまうという、飲み干すしかない仕掛けで、場をさらに盛り上げます。

上段:天狗…不安定なので置けない(長い鼻の先までたっぷりお酒が入ります)。
下段右:ひょっとこ…口に穴が空いているので置けない。
下段真ん中:おかめ…「顔を下にして置くのはかわいそう」という理由で置けない。
下段左:独楽…上記の3つの面が描かれた独楽を回して止まったときに軸の向いている方角に座っている人が、出た絵柄の杯で飲みます。
高知の日本酒は、辛口ながらも旨みがあるものが多く、お料理との相性も抜群。このべく杯を片手に、地元の人々と語らいながら飲むお酒は格別です。高知ならではの熱気ある「おきゃく」を体験してみるのも面白いかもしれませんね!
高知県では、「土佐の「おきゃく」」という高知の街全体を大きな宴会場に見立てたイベントが毎年3月に開催されており、高知の中心地で地元の人と「おきゃく」を体験できます。
また、多くの人が行き交う帯屋町商店街では、アーケードにこたつが並べられ、その場で知り合った人との交流を楽しむ人も!
期間中は、食と酒はもちろん、音楽やよさこい、アート、カルチャー等も楽しめます!
▼「土佐の「おきゃく」」について、詳しくはこちら
https://tosa-okyaku.com/
2. 人と人との絆を深める「返杯(へんぱい)・献杯(けんぱい)」の流儀!
高知のおきゃくでは、「返杯」や「献杯」という独特の作法があります!
「献杯」は、目上の人やゲストの方に敬意を込めてお酒を注ぐことです。「どうぞ、お飲みください」の気持ちを込めて注ぎ、受け取った人は、感謝の気持ちを込めてそれを飲み干します。

また、故人に対する敬意を表す際にも行われます。連続テレビ小説「あんぱん」に出ていた「献杯」もそのような意味で、寛に対しての敬意を表していたと思われます。
そして、宴会の席で献杯に続くのが「返杯」!
これは、献杯してくれた人への感謝と友情の証として、今度は自分が相手に注ぎ返すことです。「ありがとう、今度は私から!」という、高知らしい心意気が詰まっています。こうして杯を交わし合うことで、人と人との繋がりがどんどん深まっていきます。最初は少し緊張するかもしれませんが、この返杯・献杯のやりとりこそが、高知のおきゃくの醍醐味です!

3. 「はちきん」と「いごっそう」が育む酒豪県
高知県は、「はちきん(男勝りで働き者の女性)」や「いごっそう(頑固で気骨のある男性)」といった土佐弁があるように、パワフルで、そして情に厚い県民性が特徴です。そんな気質を持つ高知県民は、お酒をこよなく愛する酒豪が多いことでも知られています。
また高知県は四万十川や仁淀川など豊かな水源に恵まれていることもあり、県内には小規模ながらも個性豊かな酒蔵が点在し、それぞれのこだわりが詰まった日本酒が造られています。食中酒としても楽しめるすっきりとした辛口から、米の旨みがしっかり感じられる芳醇なタイプまで、種類も豊富です。
蔵見学ができる酒蔵もあるので、高知で日本酒を楽しむ旅をするのはいかがでしょうか。

▼高知の酒蔵について、詳しくはこちら
https://kochi-tabi.jp/gourmet/sake.html
4. まとめ:高知県独自の酒文化をぜひお楽しみください!
高知県の酒文化は単にお酒を飲むだけでなく、人々との交流や歴史、そして何よりも「楽しむ心」が詰まっています。
高知に訪れ、「酔い」旅をお楽しみください!
次回の記事もお楽しみに。ほいたらね!